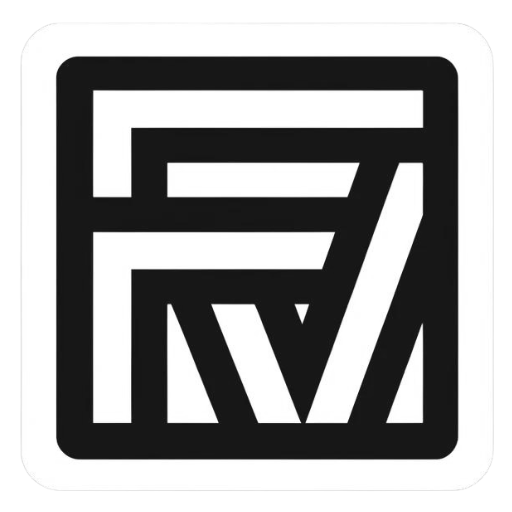2025年の兵庫県知事選挙で、現職の斎藤元彦氏が再選を果たした。この結果に対して、SNSの影響力を指摘する声は多く、実際、SNSを通じて拡散された政治的メッセージやフェイク情報が一定の役割を果たしたという分析もある。
だがこの選挙結果は、単に「SNSが強い」「テレビは弱い」というメディアのパワーバランスだけで語れる問題ではない。私たちは今、情報の「正しさ」よりも「どう出会ったか」によって、その信頼性を判断してしまうという、新しいフェーズに入っている。
この記事では、なぜSNSの情報が人々に信頼されやすくなっているのか、その背景にある心理的・構造的要因を解説する。
SNSは「能動的メディア」と錯覚される構造を持っている
SNSを使っているとき、私たちは何気なく検索し、記事や動画のサムネイルをタップし、次々と情報を取捨選択している。こうした行動がもたらすのは、単なる操作以上の感覚だ。
人間は「自分で選んだ情報」を他人から与えられた情報よりも信頼しやすい。これは心理学で言う「自己決定理論(Self-determination Theory)」の応用でもある。人は、能動的に選択した経験に価値を見出す傾向がある(Deci & Ryan, 1985)。
つまり、SNSの利用は「自分が選んだ情報だ」と錯覚しやすい構造を持っている。実際には、プラットフォームのアルゴリズムが好みに合う情報をリコメンドしているにすぎないのだが、ユーザーはそれを「自分の選択」と認識しやすい。
受動的メディアが失いつつある「信頼の演出」
一方で、テレビや新聞などのオールドメディアは、基本的に「受動的」な体験となる。番組や記事は自動的に流れてくるものであり、情報選択のプロセスに主体性を感じづらい。
この「選択感の不在」は、信頼感の低下と直結する。たとえば、新聞が正確なファクトチェックをしても、「自分が選んで見つけたわけではない」というだけで、SNSの情報より信頼度が劣るように感じてしまうケースがある。
これは単なる感情論ではなく、現代のメディア心理学が示す重要な現象だ。MITの研究では、フェイクニュースが真実よりも6倍速く拡散することが確認されており、その理由の一つとして「感情的反応や自分ごと化されやすい構造」が挙げられている(Vosoughi et al., 2018)。
ファクトチェックは効かない?――信念と認知バイアスの壁
近年の研究では、ファクトチェックの効果は限定的であることが示唆されている。特に、陰謀論や政治的立場に強く根ざした信念を持つ人々には、正確な情報よりも「自分が信じたい情報」が優先される。
これは「確証バイアス(confirmation bias)」と呼ばれる認知傾向で、人は既に信じていることに合致する情報を選び、そうでない情報を無視しやすい(Nickerson, 1998)。
たとえば、「自分で調べてDS(ディープステート)の存在を知った」と語る陰謀論支持者の多くは、検索エンジンやSNSを通じて、自ら信じたい答えにたどり着いたという感覚を持っている。この「自分で調べた感」が、情報の正確性に関係なく信頼を強めてしまう。
メディアが再び信頼を得るには「選択感の演出」がカギ
このような背景を踏まえると、オールドメディアが信頼を回復するためには、単なる正確性ではなく、「ユーザーの関与体験」を再設計する必要がある。
すでに一部のメディアは変化を始めている。
- 新聞のデジタル版は、有料会員向けにパーソナライズされた記事推薦を導入。
- ラジオは「radiko」アプリにより、番組検索・視聴の自由度が高まり能動的メディアへと変化。
- テレビ番組も「TVer」などの配信プラットフォームを通じて、「選んで見る」体験を強化している。
最も成功しているのは週刊誌かもしれない。週刊誌は「気になる記事を自分で選んで買う」という購買行動を伴うため、読者に「自分で選んだ」感覚を強く与える。これは新聞の宅配とは根本的に異なる体験だ。
結論:信頼とは「情報の正確性」より「たどり着き方」に宿る
SNS時代における信頼の構造は、情報の質や発信元だけでは説明できない。「自分で見つけた」「自分で選んだ」と感じるかどうか――この“選択感”が、信頼形成のカギとなっている。
今後、メディアが信頼を得るには、「能動的に情報と関わっている」という体験設計が不可欠になるだろう。それは単にテクノロジーの進化ではなく、人間の認知と感覚に向き合う、メディアの再設計そのものである。