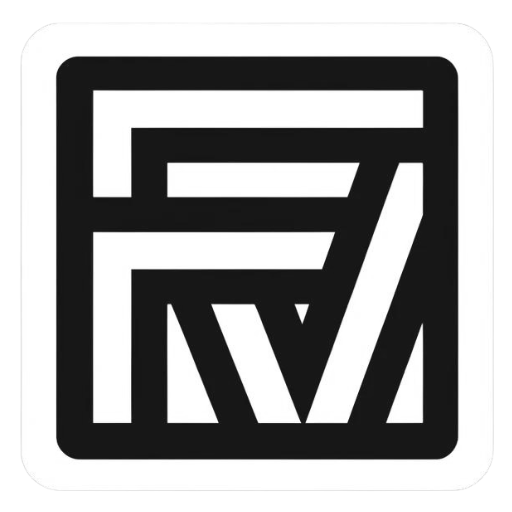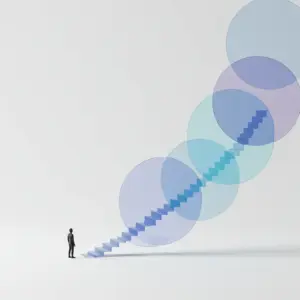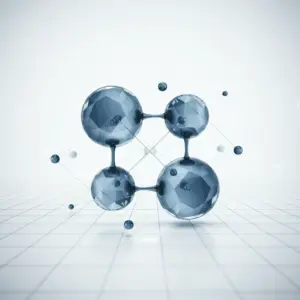Attention、Interest、Search、Action、Share──
この5つのステップで構成されるAISASモデルは、ネット時代の消費者行動を表す有名なフレームワークです。マーケティングの教科書や研修資料でも頻出ですが、実際の現場で「本当に使いこなせている」と言える人は少ないかもしれません。
「順番は覚えたけど、どうやって施策に落とし込めばいいの?」 「SNS全盛のいま、AISASはもう古いのでは?」
そんな違和感を抱いたことがある方に向けて、この記事ではAISASをフレームワーク思考で問い直します。順番を覚えるのではなく、「どこで」「誰が」「どうやって」各フェーズを生み出すかを設計するための構造へ。
フレームワークを「構造」として捉え直せば、AISASはまだまだ使える。そう実感できる視点をお届けします。
AISASとは何か?まずは原型を押さえる
AISASは、2005年に電通が提唱した消費者行動モデルです。
- Attention(注意)
- Interest(興味)
- Search(検索)
- Action(行動)
- Share(共有)
マスメディアを起点としたAIDMAに対して、AISASは「ネット検索」や「情報共有」といったオンライン特有の行動を含んでいる点が特徴です。
当時としては革新的でしたが、SNSが一般化した現代では、次のような違和感が出てきます。
AISASモデルが“古く見える”理由
消費者行動は今や直線的ではなく、むしろ“分岐”や“逆流”が当たり前になっています。
- SNSでの「Share」から「Attention」が生まれる
- 「Search」が何度もループする
- 「Action(購入)」前に「Share(比較投稿)」が起きる
つまり、AISASは“順番”ではなく“関係性”で理解しないと現実に追いつけません。
この点が、AISASが「古く見える」最大の理由です。
AISAS5要素を「問いの視点」で再定義する
✅ A(Attention)
- どこで、なぜ注目されるのか?
- 誰の言葉が信頼されるのか?(ウィンザー効果的な視点)
- 「偶発的な発見」をどう仕掛けるか?(SNSスクロール、街中広告など)
- 発信者は「顧客」か「インフルエンサー」か?
✅ I(Interest)
- どうすれば興味が持続するのか?
- 誰にとって「自分ゴト化」されているか?
- コンテンツに“解像度”があるか?(自分に関係あると感じる根拠)
- 興味を「理解」へと変えるコンテンツが設計されているか?
✅ S(Search)
- どんな“きっかけ”で検索されるのか?
- 検索の深さや横展開の幅は?
- 検索フェーズに対応した記事や導線があるか?
- 検索結果の「顔」は、信頼に値するか?(タイトル、構成、実績など)
✅ A(Action)
- どこで、何を見て意思決定されるのか?
- 比較の軸は明確か?決断の背中を押す要素は?
- 行動ハードルを下げるUXが設計されているか?(価格表示、CTA、FAQ)
- 購入・登録以外の「軽いアクション」も設計されているか?(ブックマーク、いいね、資料DL)
✅ S(Share)
- どうすれば「共有したくなる体験」になるのか?
- どのタイミングで“語られる価値”が生まれるのか?
- 共有のインセンティブは何か?(共感、感謝、話題性、承認)
- シェアする“理由”や“素材”が整っているか?(サムネ、OGP、紹介文)
AISASは“順番”ではなく“連鎖”と“設計”である
AISASは、直線的な流れではなく、要素同士が連鎖的に影響しあう“構造”です。
- Shareが新たなAttentionを生む(UGCからの流入)
- Searchが繰り返されることで、興味が深化する
- Action前に他者のShareを参照する行動も一般化
つまり、「誰が・どこで・何の目的で」各要素を起こすかを設計する必要があるのです。
AISAS×コンテンツ設計:設計できる問いに変えると何ができるか?
- SNS投稿はAttentionか?Shareか?
- LP(ランディングページ)はInterestの深化か?Searchの補完か?
- ユーザーが「検索」しているとき、どの疑問に答えるコンテンツが必要か?
- CTA(行動喚起)はどの要素の“つなぎ”に機能するか?
このように、各フェーズを「何を生み出すか」で捉えることで、コンテンツ設計や広告導線の精度が上がります。
まとめ:AISASを「記号」ではなく「設計言語」にする
AISASは、ただの流れを覚えるフレームではありません。
- A・I・S・A・Sのそれぞれを「問い」として再定義する
- “誰が・どこで・なぜ”各要素を起こすのかを設計する
- ShareがAttentionを生み出す構造を描く
このように、AISASを「記号」ではなく「設計言語」として使うことで、マーケティング施策の質は格段に向上します。
「あなたの施策は、誰のShareから始まっているか?」
そんな問いを自分自身に投げかけながら、AISASを再活用してみてください。