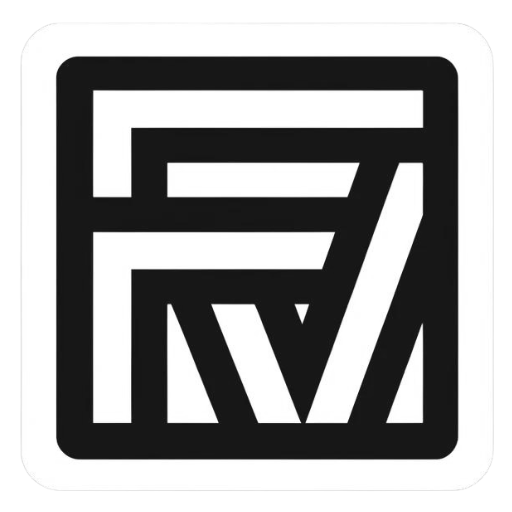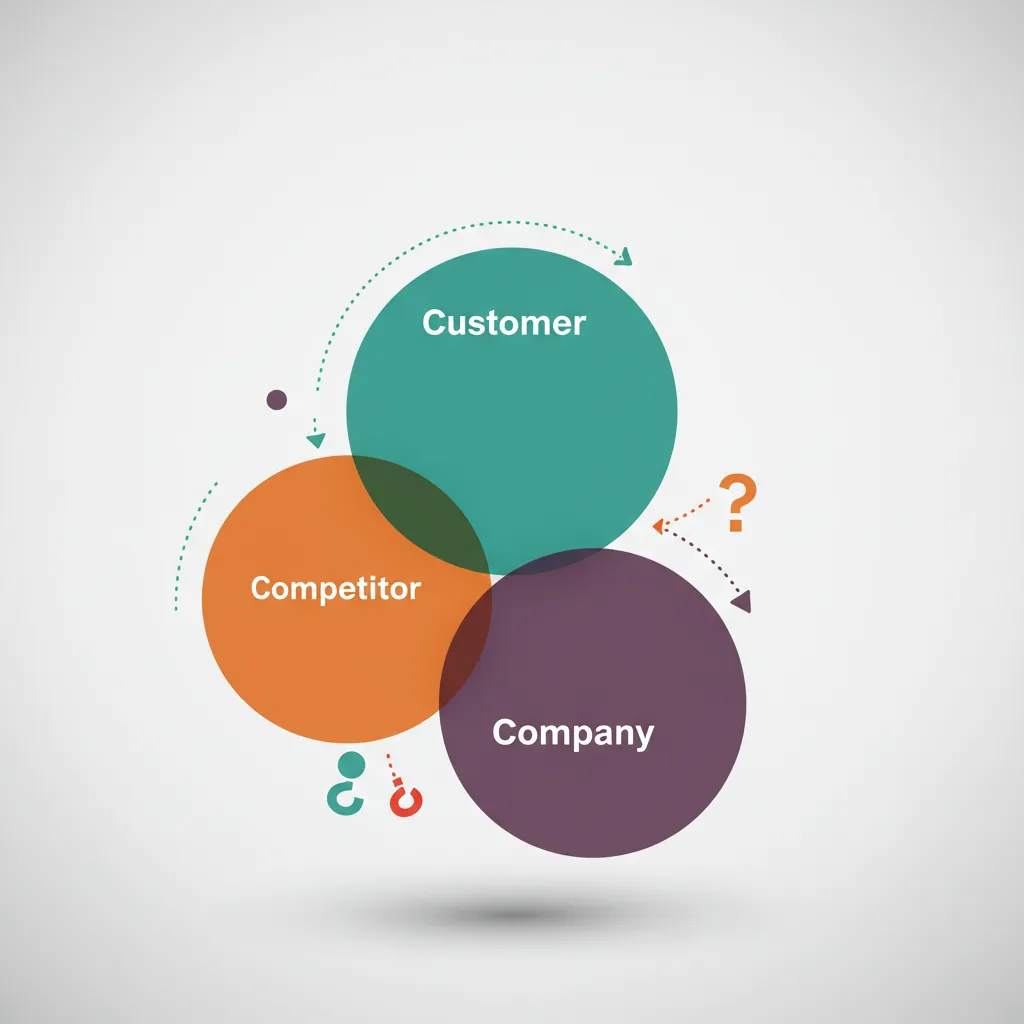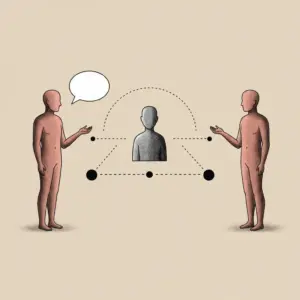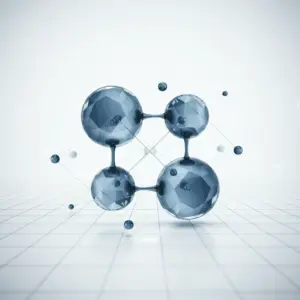「とりあえず3Cで整理してみました」
企画会議や事業計画の資料で、よく見る一文です。 Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)をそれぞれ書き出して、戦略を立てようとする──マーケティングの基本中の基本。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてほしいのです。
その3C分析、本当に“考える”助けになっていますか?
- 書いたはいいけど、次のアクションに繋がらない
- 情報は整理できたのに、戦略がぼやけている
- 顧客・競合・自社の関係性がピンとこない
…もしそんな感覚があるなら、それは「3Cを埋める作業」になっているサインかもしれません。
本来、3C分析は「問いを立てるためのフレームワーク」です。 情報を“当てはめる”ためではなく、“見えない構造を捉える”ための思考補助線。
この記事では、そんな3C分析を 「フレームワーク思考」で再解釈してみたいと思います。
- なぜ顧客はそれを選ぶのか?
- 競合とは、本当に“他社”なのか?
- 自社の価値は、どこで意味を持つのか?
あなたのビジネスの問いが、少しでも深く・鋭くなるきっかけになれば嬉しいです。
フレームワークは“図”ではなく“問い”である
多くの人はフレームワークを「便利な図解」として使おうとします。 でも、本質は逆です。
フレームワークとは、複雑な現実を分解して「問いを立てやすくするための補助線」です。
たとえば──
- 顧客って“誰”なのか?ではなく「なぜそう行動するのか?」
- 競合って“どこ”なのか?ではなく「何がその行動を妨げているのか?」
- 自社って“何が強み”なのか?ではなく「どの文脈で意味を持つのか?」
3C分析もこのように、“静的に埋める”のではなく、“動的に問いを立てる”ための思考装置として使い直すと、全く違う景色が見えてきます。
3Cを一つずつ再定義してみよう
Customer:「誰が買うか」じゃなくて「なぜその選択を?」
「顧客は30代女性」「市場規模は●億円」──これ、情報としては正しいけど、思考にはつながりません。
大事なのはその人たちが「なぜ今、その選択をするのか?」という行動の背景です。
- どんな状況で、どんな課題を感じていて
- どんな理屈・感情・社会的動機で選んでいるのか
ここまで掘ると、「ターゲット層」ではなく「文脈」が見えてきます。 そして、選ばれない理由(無関心・放置・他の手段)もまた重要な“構造”です。
Competitor:「同業他社」ではなく「選択肢すべて」
競合を「同じようなサービスをやっている会社」と捉えると、見誤ります。 本当の競合は、「顧客が“それを選ばない”という選択肢すべて」です。
- 代替手段(手作業、無料サービス、自作、友人に頼る)
- 時間の使い方(そのお金で他のものを買う、その時間を別のことに充てる)
- 無関心(そもそもこの分野に対する優先度が低い)
つまり、競合とは「顧客の意思決定プロセスで比較される対象すべて」なんです。
Company:「強み」ではなく「どこで意味を持てるか?」
自社の“強み”を語るのは簡単です。 でも、それが顧客にとって「意味がある」とは限らない。
むしろ、「その文脈で、その顧客にとって相対的に価値があるか」が重要です。
- スペックではなく、理解されやすさ
- 機能ではなく、信頼される導線
- ボリュームではなく、ちょうどよさ
つまり、「自社が意味を持てる場面(コンテクスト)」を定義することが、本当のポジショニングなのです。
3C分析の順番、逆にしてみたら見えたもの
多くのフレームワークでは「Company→Competitor→Customer」の順で進めがちですが、フレームワーク思考で使うなら逆が良いです。
- まずはCustomer:顧客行動の地図を描く
- 次にCompetitor:顧客の選択肢として現れる競合を見つける
- 最後にCompany:その中で自社がどこに意味を持てるかを見極める
これだけで、「3Cに情報を埋める」から「顧客と向き合う思考構造」に変わります。
ケーススタディ:思考が深まった3Cの再設計
事例1:SaaSの競合は“Excel”だった
あるSaaSが売れない理由を競合他社だと思い込んでいたが、実は多くの顧客は「Excelでなんとかしている」だけだった。 →“便利さ”ではなく“乗り換えコスト”という壁が本当の競合だった。
事例2:地方カフェの敵は“コンビニコーヒー”
地元密着で差別化していたカフェが、集客が伸びない原因を同業の新店舗と考えていた。 でも実際は「ついでに買える」コンビニの方が“日常の選択肢”だった。 →求めるべきは“非日常の動機づけ”という新たな意味づけだった。
他のフレームともつなげてみよう
3C単体ではなく、他のフレームと接続することで、戦略の解像度が上がります。
- STP分析:セグメント→ターゲティング→ポジショニングに3Cを使う
- バリュープロポジションキャンバス:CustomerとCompanyの接点を具体化
- SWOT分析:Companyを内側と外側から再整理する際に活用
3Cは“最初の地図”として、他のフレームの下地にもなります。
まとめ:「問いが浅いと、答えも浅い」
3C分析を「なんとなくやる」のは簡単です。 でも、それで戦略が深まることはほとんどありません。
大切なのは、「3Cで何を問いかけるか?」ということ。
- Customer:選ばれる理由と、選ばれない理由を文脈で問う
- Competitor:顧客の選択肢すべてを俯瞰して見る
- Company:意味を持てるポジションを“相対的に”探す
これができたとき、3C分析は「情報整理のツール」から「行動につながる思考の武器」へと進化します。